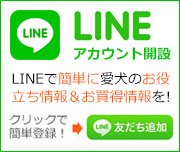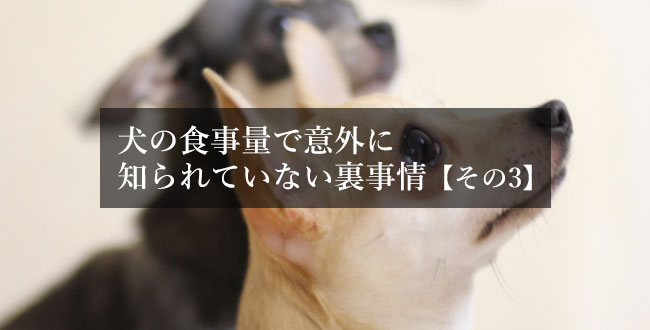
犬の食事量で意外に知られていない裏事情【その3】

前回からの食事量の続きとして大型犬以外の普通の子犬や成犬の食事量についてお話します。
愛犬の食事量は下記の方法で調整するとその子その子の適正量に合わせることができます。
1・20分で食べきる量を与える犬は無限に食べ続けると考えている人がいますが、そうではなく、空腹が満たされるまでは猛烈に食べますが、
満たされると、ピタッと食べなくなります。
そして、この量で、軟便になるようであれば、
2・軟便にならない量までフード量減らすこれが、犬の食事の適正量です。
あとは長期的にみて、太りすぎならこの量から減らしてゆきます。
このことで体重のコントロールも適切に調整できます。
本当にフードを必要としているか、単に過剰な欲求で欲しがっているかは、愛犬の目を見ます。
本当に栄養が足らなくてフードを欲しがっているときの目と、よくばりで食べたがっているときの目は表情が違うのです。
人の子供でも同じですよね。
本当にお腹が空いているときには必死で食べたがります。そう訴えます。
でも一方でオヤツやお菓子なども欲しがりますが質が違いますね!
それを愛犬でも見分けてあげることが大切となります!
食事量の調整の仕方
 食事量の調整の仕方は色々な方法がありますが、
食事量の調整の仕方は色々な方法がありますが、
私へのご相談は、
◆食事量が極端に少なすぎる(真面目に規格を厳守)とか
◆多すぎる(無秩序に与えすぎ)の場合がとても多いです。
犬をたくさん飼った経験がある人は、犬が無秩序に食べ続けることがないことを知っていると思います。
ちゃんと適正量になるとピタッと食べなくなります。
それを小さい時から、ずっとヒモジイ思いをさせてきた子は、その記憶で過剰に食べたがるということが起きます。
小さいころや成長期に食事制限をしすぎると、子犬の代謝が落ち、飢餓遺伝子が活性化して太りやすくなります。
基本的に食事制限は1歳以降での調整になります。
基本的に食事制限は、1歳以降での調整で太りすぎを防止してゆくことが役立ちます。
あまりにお腹を空かせすぎると、石を食べたり、ストッキングやおもちゃまで食べたりして、とても危険でもあります。
このあたりは、ちゃんと説明したものが少ないので、また機会があればお話したいと考えています。
あと、食事の変更はできるだけゆっくりと行われるのが良いです。
犬を規格品としてみないように、自分や家族と同じように食べる量に個性があること。
そして、飼主としてそのような配慮をして飼育してあげて頂くことを心掛けていただければ幸いです