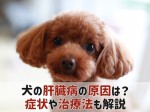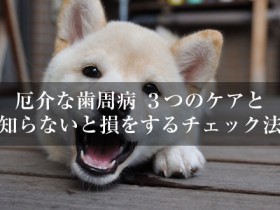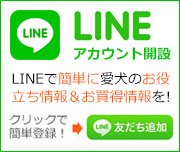犬が肝臓病の食事を食べない原因と5つの対処法
- 2022/10/31
- 肝臓の病気について

犬が肝臓病の食事を食べない原因と5つの対処法
犬は慢性肝臓病が進むに連れて、食欲低下などの症状が現れてきます。
また、療法食は通常のドッグフードと味が異なるため、食いつきが悪くなることがあります。
愛犬が肝臓病の食事を食べない時は、
- 療法食を始めるときは少しずつ切り替える
- フードを温める
- フードを柔らかくする
- 食事を数回に分けてあたえる
- フードをトッピングする
など、食欲をそそるような工夫をしてみましょう。
以下の項目で詳しく解説していきます。
目次
犬が肝臓病の食事を食べない時の対処法

1.療法食を始めるときは少しずつ切り替える
肝臓病用の療法食を始めるときは、1か月程度の時間をかけて少しずつ切り替えていくのがポイントです。
肝臓病用の療法食は、通常のドッグフードと味が異なります。
そのため、急にフードを切り替えると愛犬がとまどい、食事を食べなくなってしまうことがあります。
愛犬が普段食べているドッグフードに肝臓病用の療法食を徐々に混ぜ、少しずつ慣らしていきましょう。
また、肝臓病療法食は少量でも必要な栄養をしっかりと摂取できるよう、カロリーが高めに作られています。
そのため、一般的なドッグフードと比べると、療法食を与える量は少なくなります。
療法食の袋などに記載されている食事量に基づいて、適切な量を与えるようにしましょう。
療法食への切り替えについて困った時は、以下の記事も参考にしてみてください。
2.フードを温める
フードを温めて香りを増すことで、食欲をそそる効果が期待できます。
犬は嗅覚が発達しており、匂いで食べ物を判断します。食事は温めることでフードの香りが増すため、犬の食欲を高める効果があります。
温める際は、電子レンジやお湯などで常温から人肌程度になるよう調整します。
温めすぎると愛犬がやけどしてしまう場合もあるので、飼い主が指などで触って温度を確認してから与えるようにしましょう。
3.フードを柔らかくする
肝臓病が進行して食欲が低下すると、食物を噛むのがつらくなることがあります。
そのため、肝臓病療法食がドライフードの場合は水分を加えて柔らかくするのも効果的です。
ドライフードに水分を加えることで不足しがちな水分を補給でき、脱水症状を防ぐ効果も期待できます。
ドライフードに水分を加えるときには、ぬるま湯を注ぐと香りが増して嗜好性が高まります。
ただし、熱湯を注ぐとドッグフードの栄養素が壊れてしまうため、必ずぬるま湯を使いましょう。
4.食事を数回に分けてあげる
肝臓病の食事を食べない場合、食事を数回にわけて少量ずつあたえることで、食事量が増加することもあります。
肝臓病により肝炎を発症すると、一度に食べられる量が少なくなります。
そのため、一回の食事量を減らして、その分、食事の回数を増やすことで、合計食事量の増加を期待できます。
5.フードにトッピングをする
愛犬が療法食をあまり食べないときは、好きな食物をトッピングしてみる方法もあります。
ただし、肝臓病の犬がタンパク質や銅などを摂取しすぎると、肝機能に負担がかかり肝臓病の症状を悪化させてしまうおそれがあります。
トッピングする前に獣医師と相談して、あたえてよい食物と量を確認しましょう。
肝臓病の犬が食事を食べなくなる理由

肝臓の炎症による食欲低下
肝臓病が進行すると、肝細胞の壊死、肝硬変などにより肝機能が低下すると、低アルブミン症、BUNの低下、高ビリルビン血症、高アンモニア血症などを発症します。
その痛みや気持ち悪さなどから食欲が低下してしまいます。
また、味覚や嗅覚が変化して、食欲不振になることもあります。
フードの味の変化による食欲低下
肝臓病療法食へ切り替えにより、フードの味の変化が気になり食事量が低下することもあります。
「療法食を始めるときは少しずつ切り替える」でご紹介した、1か月程度の時間をかけて少しずつ切り替えていく方法を試してみましょう。
吐き気・下痢などの諸症状による食欲低下
肝臓病は、上記で説明した症状の他にも吐き気(嘔吐)や下痢など、さまざまな症状を引き起こします。
これらの諸症状も食欲不振の大きな原因となります。
犬の肝臓病の療法食とは?療法食が重要な理由

犬の肝臓病の療法食とは、肝臓の負担となる栄養素(タンパク質・銅など)を適量に抑え、ミネラルやエネルギーの量を調整したフードです。
肝臓の療法食の他にも、心臓・膵臓・皮膚・消化器、尿路結石症や食物アレルギーのサポートなどさまざまな療法食があり、症状に合わせて栄養バランスの量が調整されています。
犬の慢性肝臓病は、進行しても適切な治療や食事療法により肝機能を回復できます。そのため、肝臓病を発見したら、適切な治療と食事療法を開始することが重要です。
慢性肝臓病の犬に適切な食事療法をおこなうことで、命に関わるような肝性脳症や肝硬変に対して効果的に対処ができます。
そのため適切な治療や食事療法がとても大切と考えられています。
ただし、療法食は獣医師の診断・指導に基づいた食事療法として与える必要があります。
飼い主の中には、肝臓病を発症する前や子犬のときから予防目的で療法食を与えたがる方がいますが、健康な犬に療法食を与えると必要な栄養素を充分に摂取できないおそれがあるので控えましょう。
療法食ではない食べ物をあげてもいいの?
肝臓病の犬の食事は、肝臓に負担をかけるさまざまな栄養素を適切に抑えることが重要です。
そのため、肝臓病の療法食に切り替えたあとは、従来のドッグフードやおやつなどをあげることは控えましょう。
また、肝臓病で控えるべきタンパク質や銅などの栄養素は多くの食品に含まれているため、手作りでご飯を用意するのは極めて困難です。
適切な食事療法をおこなわないと、肝臓病の進行を早めてしまうおそれがあります。そのため、肝臓病の犬の食事には、最適な栄養・カロリーを配合した療法食を活用しましょう。
肝臓の働きと肝臓病について
肝臓は、タンパク質、炭水化物、脂質など重要な栄養素の代謝を行う重要な臓器です。消化器で吸収した栄養を処理し毒素の解毒を担います。免疫の調整機能の役割も担っています。このように体の活動を支える重要な働きを支えています。
肝臓病とは、肝機能が何らかのダメージにより低下し、肝臓本来の働きができなくなる病気です。そのため、黄疸、腹水、肝性脳症などさまざまな症状を引き起こします。
犬の肝臓病は、原因や症状により慢性肝臓病と急性肝臓病の2つに分かれます。
犬の肝臓病の原因
犬の肝臓病は、慢性と急性でそれぞれ原因が異なります。
⇒犬の肝臓病の原因について
慢性肝臓病の原因
- 老化にともなう肝機能の低下
- 遺伝的な銅の蓄積による肝機能の低下
- 原因が特定できない突発的な肝機能の低下(感染、薬剤、毒物など)
急性肝臓病の原因
- 肝毒性のある物の誤食(キシリトール、人の風邪薬など)
- 感染症などによる急激な肝機能障害(犬アデノウイルス1型、レプトスピラ、敗血症など)
- 治療薬(てんかん治療薬、抗がん剤、抗生剤)
…など。
犬の慢性肝臓病・進行ステージごとの症状
犬の慢性肝臓病は、病気の進行状況により変化します。
犬の慢性肝臓病は、血液検査はALT(GPT)、AST(GOT)、ALP、GGT(γ-GTP)などの数値、低アルブミン血症、BUN低下、高ビリルビン血症、高アンモニア血症、総胆汁酸(TBA)の項目を重視します。
レントゲン検査(X選検査)、エコー(超音波診断)なども加え、3つの進行レベルに分類されます。
(※スマホでご覧の場合表を右にスクロールできます)
| ステージ | 症状 | 治療・対策 |
|---|---|---|
| Ⅰ 初期 |
・初期・早期の慢性肝臓病の状態。 ・一般的に無症状 ・ほとんどの犬が元気で食欲もあるため、異常に気づかないこともある。 |
・肝臓に負担となる食物などを与えない。 |
| Ⅱ 中期 |
・中期の慢性肝臓病の状態。 ・食欲の低下や嘔吐などの症状。 ・血液検査で肝機能の指標となる数値である、ALT、ASTなどの上昇がみられる。 |
・肝臓病用の食事療法を行う。 ・原因や疑わしいサプリメント、食材、薬などを排除する ・原因にあわせた治療を行う |
| Ⅲ 末期 |
・末期の慢性肝臓病の状態。 ・肝硬変が進み重篤な症状がみられる。 |
・肝臓病用の食事療法を行う。 ・ステロイド療法、キレート療法など原因にあわせた治療を行う。 |
ステージ1(ステージⅠ)・初期、早期の症状
- 一般的に無症状
- 愛犬が少しだるそうな様子
- 血液検査で肝機能異常が見つかる
犬の慢性肝臓病進行レベル1の段階では、ほぼ無症状です。
しかし、愛犬が以前のように走り回ったり、長時間の活動が減ったりなど、愛犬が老化した印象を受けることが多いようです。
血液検査で異常がみられ、肝臓数値のALT、ASTなどに異常がみられます。
慢性肝臓病を早期発見するためにも、愛犬がシニア期(6~7歳)に入ったら、1年に1~2回の定期健康診断を行うようにしましょう。
進行レベル2(ステージⅡ)・中期の症状
- 無症状〜軽度の症状
- 急な老化を感じさせる
- 反応が鈍くなったり、散歩への興味が薄れる
- 多飲
- 食欲不振
- 体重の減少
- 散歩を嫌がる
- 静かにしている時間が増える
- 嘔吐
犬の慢性肝臓病進行レベル2の段階で一番多くみられる症状は、嘔吐です。
嘔吐が起こる原因として、肝臓に毒性のある薬、サプリメント、食材、遺伝的な銅蓄積などにより肝細胞がダメージを受けたことによります。
この時、愛犬が摂っているいるもの(薬、サプリメント、食材など)に注意しましょう。
遺伝的な銅の蓄積による肝障害の場合はキレート療法などを検討します。
上記の他に、体重の減少(痩身)、散歩をしても下を向いている、寝床から動かないで静かにしている時間が多くなる(嗜眠)、下痢などの症状も現れます。
血液検査ではALT(GPT)、AST(GOT)、ALP、GGT(γ-GTP)などの数値の上昇がみられます。
この段階でかかりつけの動物病院の指導に従い肝臓病用の食事療法へ切り替えることが、慢性肝臓病の回復と健康維持に役立つことが多いです。
しかし、肝細胞のダメージや、食べ慣れたドックフードでないことから、犬が療法食を食べてくれないこともあります。
愛犬が肝臓病の療法食を食べない場合は、「犬が肝臓病の食事を食べない時の対処法|肝臓病の原因や症状も」の記事を参考にしてください。
進行レベル3(ステージⅢ)・末期の症状
- ぐったりして、見るからに元気がない
- 大半の時間を寝て過ごす
- 嘔吐
- 下痢
- 黄疸
- 腹水
- 脳性肝症(後天性門脈シャント)
犬の慢性肝臓病進行レベル3の段階は、肝臓病末期の状態です。
肝硬変が進行しており、生命維持のため原因に合わせた治療が必要になります。
愛犬は見るからにつらそうにぐったりした状態で、散歩も行かず、大半の時間を家の中で寝て過ごすようになります。
また、嘔吐などが強くなる症状も現れます。
愛犬は身体がつらく、呼びかけに反応しないことが多くなりますが、愛犬自体は元気な時と同じように飼い主の愛情を必要としています。
主な治療はかかりつけの動物病院に任せ、飼主は、話しかけたり、やさしく撫でてあげるなど愛犬に愛情が伝わることも意識して配慮してあげましょう。
犬の肝臓病の治療法
傷ついた肝機能は適切な治療と食事療法により回復することができます。そのため、犬の慢性肝臓病は、獣医師の診断・指導のもと、適切な治療や食事療法などで肝臓病の回復を促すことが重要です。
なお、重い急性肝臓病は命の危険がありますが、その場合でも、点滴や投薬などの適切な治療を動物病院で受けることで肝機能が回復する可能性もあります。
急にぐったりする、嘔吐を繰り返すなどの急性肝臓病の症状がある場合は、一刻も早く獣医師による診察が必要です。
愛犬に良い食事と、食べやすくなる工夫を
犬の肝臓病は療法食をもとにした食事管理が重要ですが、肝臓病が進行すると吐き気などの原因により食欲が低下します。
愛犬が食事を食べやすくなるよう、今回ご紹介した方法を活用して愛犬の食事をサポートしましょう。