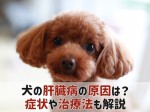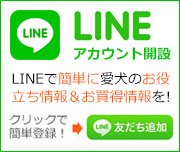犬の肝臓病に療法食をおすすめする理由
- 2022/10/31
- 肝臓の病気について

犬の肝臓病の療法食を徹底解説
犬の肝臓病(肝機能不全)の療法食について詳しく説明します。
犬の療法食とは、療法食の種類、健康な犬のドッグフードとの違い、療法食の栄養素、療法食を与えるときのポイント、療法食を食べない時の対処法、療法食は手作りできるのかなど、犬の肝臓病用療法食について徹底解説します。
目次
犬の肝臓病の療法食とは?

犬の肝臓病の療法食とは、肝臓の負担となる栄養成分・ミネラルなどの量を調整したフードです。
療法食は、一般的なドッグフードとは異なり、獣医師の診断・指導に基づいた食事療法として与える必要があります。
犬の肝臓病の療法食とは、肝臓の負担となる栄養成分・ミネラルなどの量を調整したフードです。
療法食は、一般的なドッグフードとは異なり、獣医師の診断・指導に基づいた食事療法として与える必要があります。
肝臓の療法食の他にも、心臓・膵臓・皮膚・消化器、尿路結石症や食物アレルギーのサポートなどさまざまな療法食があり、症状に合わせて栄養バランスの量が調整されています。
そもそも犬の肝臓病とは?

犬の肝臓病(肝機能不全)とは、血液中に溜まった老廃物などを尿と一緒に排泄する、肝臓本来の働きができなくなる病気です。
犬の肝臓病(肝機能不全)は、
- 老化などにより肝機能が低下する慢性肝臓病
- 誤飲・事故などによる急性肝臓病
以上の2種類があります。
どちらも病状が悪化すると、嘔吐、下痢、元気消失、食欲喪失などの症状を引き起こすため、適切な治療が必要です。
なぜ療法食が慢性肝臓病の犬に重要なの?
犬の慢性肝臓病は、適切な治療をすることで回復することができます。
そのため、慢性肝臓病を発見した場合、適切な治療や食事療法を開始することが重要です。
慢性肝臓病の犬に適切な食事療法をおこなうことで、病気から回復させる効果があります。
犬の肝臓病療法食・3つの特徴

1. タンパク質
犬の肝臓病療法食は、タンパク質の量を適切に抑えているのが特徴です。
肝機能が低下してくると、タンパク質を代謝からアンモニアが充分にコントロールできなくなります。
その結果、アンモニアが体内で高濃度となり、肝性脳症など危険な症状を引き起こします。
そのため、肝臓病の犬には、タンパク質を制限した食事を与えることが重要です。
しかし、タンパク質は犬の食事に必要不可欠な栄養素なので、適切量を摂取できるよう調整された食事が必要になります。
2. 銅
あるタイプの慢性肝臓病の犬は銅を効率的に排出できなくなるため、食事に含まれる銅を制限するか、銅を吸収しずらくすることで銅蓄積をコントロールする必要があります。
銅が関連する慢性肝臓病の犬が一般の食事を摂取すると銅蓄積を引き起こし、肝機能の低下を引き起こします。
銅はさまざまな食材に含まれておりが、特に赤肉やレバーなどの臓物の銅含有量が多いため適切量に調整するのが難しいとされています。
特に手作り食(ハンドメイドの食事)では銅の含有量が多くなると懸念されています。
そのため、最適なバランスに調整された肝臓病療法食を与えることが、愛犬のQOL(生活の質)維持につながります。
3. エネルギー
慢性肝臓病の犬は肝臓機能の低下から低血糖になりやすいため、療法食は効率的にエネルギーを補給できるよう調整されています。
肝臓病の食事管理のためにタンパク質を制限すると、食事から得られるエネルギー量が低下します。
そのため、療法食では、肝臓に負担のかからないよう調整された栄養により健康維持に充分なエネルギー量を満たせるよう、炭水化物、脂肪量がバランスよく調整されています。
犬の肝臓病療法食の種類
ドライフードとウェットフードの違い
肝臓病療法食にはドライフードやウェット缶などの種類があります。
ドライフードは栄養を効率的に摂取でき、ウェットは嗜好性が高くなる傾向があります。
そのため、最初はドライフードの小袋から試してみることをおすすめします。
なお、ドライやウェットなどの区分は、一般社団法人ペットフード協会により以下のように分類されています。
| 形状 | 特徴 |
|---|---|
| ドライ | 製品水分10%程度以下のフード。加熱発泡処理された固形状のもので、袋に入っているものがほとんどです。 |
| ソフトドライ | 製品水分25~35%程度のフードで、加熱発泡処理されています。 |
| セミモイスト | 製品水分25~35%のフードで、押し出し機などで製造され、発泡していないものです。 |
| ウェット缶詰 | 水分75%程度で、品質保持のために殺菌工程を経て、缶詰に充填されたフード。 |
原材料の違い
療法食の原材料は、メーカーにより異なることがあります。
主原料となる肉類では、鹿肉、鶏肉(チキン、ターキーなど)、豚肉、牛肉、カンガルー肉、魚肉(サーモンなど)など、さまざまなタイプがあります。
また、アレルギー対応などの目的で、穀物をふくんでいないグレインフリーやグルテンフリーのタイプもあります。
原材料はペットフードの袋や缶詰に記載されていますので、不要な添加物が含まれていないかなどもあわせて確認してみましょう。
原材料の選び方については、獣医師と相談のうえ、愛犬の好みやアレルギーなどを考慮しましょう。
療法食を与えるときのポイント

獣医師の指導のもとで与える
療法食は、獣医師の診断・指導のもとで適切量を与える必要があります。
肝臓病を発症する前から、予防の目的で肝臓病療法食を与えたがる飼い主がいますが、健康な犬に療法食を与えると必要な栄養素を充分に摂取できないおそれがあります。
新鮮な水を与える
肝臓病が進行すると、たくさんの水を飲みますが、同時に多尿となる場合が多く、その場合は体内の水分量を確保できず、脱水症状になる危険性があります。
そのため、いつでも新鮮な水を飲めるように飲水を頻繁に交換する、水が飲める場所を複数設置するなど、愛犬が水分をしっかり摂れる環境を用意しましょう。
犬が肝臓病療法食を食べないときは?
療法食は通常のドッグフードと味が異なるため、急にフードを切り替えると愛犬が食事をあまり食べなくなる可能性があります。
そのため、肝臓病療法食への切り替えは、1週間〜1か月程度の時間をかけて、これまでのドッグフードから療法食へ少しずつ変更していくのがポイントです。
慢性肝臓病はステージが進むほど食欲の低下がみられます。愛犬の食欲が低下してきた場合は消化吸収を良くして食欲をそそるようにするため、以下のように工夫してみるのもおすすめです。
- フードを温めて匂いを増す
- ドライフードに水分を加えて、ウエットフードのように柔らかくする
- 食事を少量ずつ数回に分けてあげる
療法食への切り替えについて困った時は、以下の記事も参考にしてみてください。
療法食とその他ドッグフードとの違いは?
犬や猫のペットフードは「ペットフードの表示に関する公正競争規約」により、以下のように分類されています。
- 総合栄養食
- 間食(おやつ、トリーツ)
- 療法食
- その他の目的食
療法食と総合栄養食の違い
療法食は、特定の病気や症状をもつ犬のために栄養バランスが調整されたドッグフードです。
獣医師の診断・指導のもとで与える必要があります。
一方、総合栄養食は健康な犬の主食として与えることを目的としたドッグフードです。
そのため、適切な量の総合栄養食と新鮮な水を与えることで、健康を維持できるよう栄養素がバランスよく調整されています。
年齢や体重に合わせて栄養基準が設けられており、1日に与える量や回数などが、年齢や体重に応じて表示されています。
子犬用・成犬用・シニア用などのライフステージに合わせたものや犬種別など、それぞれに合わせた栄養構成のフードがあります。
療法食と機能性ペットフードの違い
機能性ペットフードとは「その他の目的食」に分類されるもので、特定の栄養の調整やエネルギー補給などを目的としたドッグフードです。療法食のように病気の治療や食事療法を目的としたフードではありません。
人間の「機能性食品」のように、健康維持のためのサプリメントや栄養補助食品などの位置づけとして考えましょう。
肝臓病用の療法食は手作りできる?

飼い主の中には、肝臓病の犬のために何かしてあげたい気持ちなどから肝臓病食を手作りする方がいます。
しかし、肝臓病の犬の食事は、「犬の肝臓病療法食・3つの特徴」で説明したように、さまざまな栄養素・エネルギーの調整が必要です。
そのため、肝臓病のごはんを手作りで用意するのは極めて困難です。
また、ネットにはさまざまな情報があるため、それらの不確かな情報をもとに肝臓病食を手作りすると、逆に愛犬の健康を損なう危険があります。
大切な愛犬のために、肝臓病に最適な栄養・カロリーを配合した療法食の活用をおすすめします。
犬の肝臓病には療法食でケアを
犬の慢性肝臓病は、一度かかってしまうと肝臓の機能回復は見込めません。
そのため、肝臓病を早期に発見し、早期に食事療法を始めることが愛犬の健康を長く維持するために重要です。
肝臓病に最適なタンパク質、炭水化物、リン・カリウム・亜鉛などのミネラル、エネルギーが計算・調整された療法食を取り入れ、愛犬の肝臓の健康をサポートしましょう。