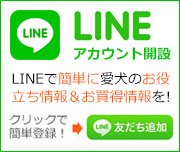犬の肝臓病に良い食材は?肝臓病の原因や症状についても解説
- 2022/10/31
- 肝臓の病気について

犬の肝臓病に良い食材は?食べていいものを解説
肝臓病(肝炎)の犬には、肝機能に負担をかける栄養素を制限する必要があります。
そのためには、以下の栄養素を含む食材を調整することが重要です。
- タンパク質を含む食材の制限
- 銅含有量が少ない食材
- 低血糖を予防する食材
これらの栄養素を含む代表的な食材と、肝臓病のために最適な栄養バランスを配合した肝臓病療法食について詳しく解説していきます。
目次
犬の肝臓病に良い食材とは?

1.タンパク質を含む食材は食べる量に注意が必要
肉類に多く含まれるタンパク質は、犬に必要不可欠な栄養素です。タンパク質は肝臓で代謝されたアンモニアは尿とともに体外へ排泄されます。
しかし、肝臓病により肝機能が低下すると、タンパク質を代謝するときに出るアンモニアを十分に排泄できなくなります。
排出できないアンモニアは体内に蓄積され、肝性脳症などを引き起こします。
そのため、肝臓病の犬はタンパク質の摂取量を制限する必要があります。
| タンパク質が含まれる主な食材 |
| 鶏肉、豚肉、牛肉、馬肉などの肉類、鮭・白身魚などの魚類、卵、チーズ、など |
2.銅含有量が少ない食材
慢性肝臓病の犬に、銅含有量を抑えた食事を与えることで銅が関与して起きる慢性肝臓病に対して有効です。
しかし、銅はさまざまな食材に含まれており、特に赤肉やレバーは銅の含有量が多いため避ける必要があるといわれています。
日本の古来からの漢方や和漢の考えから悪い臓器と同じ臓器を食材として治すという考えがありますが、犬においては遺伝的に銅蓄積する疾患があるため、人の治療を犬の知識がなく適用することは大変な危険があります。
犬には肝臓病でも良質な肉が必要ですが、あえてリスクを増すようなトッピングで赤肉を加える、レバーを肝臓の治療用の食材とすることは避けたいです。
手作りでごはん(ハンドメイドの食事)を用意すると銅を過剰に与えてしまうリスクについて獣医内科学テキストにおいても指摘されています。
そのため、肝臓病の犬の食事には、栄養素が考慮された最適なバランスで調整した肝臓病療法食を活用がおすすめです。
| 銅が多く含まれる主な食材 |
| 牛・豚・鶏など家畜の肝臓(レバー)、心臓(ハツ)、さつまいも、納豆など |
| 銅が少ない食材 |
| ごはん(精白米)、パン、麺類、タピオカ、ピュアオイルなど |
3.低血糖を予防する食材
肝臓病になると血糖のコントロールが難しくなり低血糖が起こりやすくなります。そのため低血糖を起こしにくくするために炭水化物が重要となります。
血糖は細胞のエネルギー源として欠かせない栄養素です。
しかし、肝臓病が進行すると肝臓の血糖を生成する能力がダメージを受けるため、低血糖などを引き起こします。
肝臓病の回復において、低血糖は大きな負担となるため、適切な血糖を調整できる食材が良いとされています。
| 安定した血糖を維持しやすい主な食材 |
| ごはん(精白米)、パン、麺類、タピオカなど。 |
犬の慢性肝臓病と食べていい食材の関係

犬の肝臓病とは
犬の肝臓病とは、肝臓がダメージを受けて機能が低下し、肝臓本来の働きができなくなる病気です。
⇒犬の肝臓病について詳しくはこちら
肝臓の働きは主に3つあります。
必要な物を作る(精製)、必要な物を貯める(貯蔵)、不要なものを処分する(解毒)ことです。必要な物を作るとは、人間は食物から栄養を吸収しますが、消化管の小腸からアミノ酸などの栄養を吸収し血液で肝臓へ運びます。
肝臓では運ばれてきたアミノ酸などから、たんぱく質や、糖質、脂質、ビタミンやミネラルなどを製造します。
必要な物をためるとは、吸収されたブドウ糖からグリコーゲンを製造し肝臓に貯めこむことができ、ブドウ糖が必要なときにはグリコーゲンを分解し血液中に放出して血糖値を安定させます。
肝臓はアンモニアを尿として体外に排泄するなど、体の活動を支えるための働きなど、重要な活動を担っています。
犬の肝臓の働きについて、詳しくはこちらの記事で解説しています。
犬の肝臓病は原因や症状により、以下の2つに分かれます。
- 慢性肝臓病…特定の難しい感染・薬剤・毒素などによる肝機能の低下が原因
- 急性肝臓病…感染、化学物質・薬品による中毒が主な原因
このうち、多くの犬が発症するのが慢性肝臓病です。肝炎のうちの6割が慢性肝炎と言われています。
犬の慢性肝臓病は、多くが原因がはっきりとは突き止めれない「突発性慢性肝炎」と呼ばれる肝臓の組織が傷つき、肝機能が低下する病気です。
慢性肝炎の中で次に多いのが銅関連性慢性肝炎といわれるもので、遺伝が原因です。銅を代謝して排泄させる遺伝子の異常(専門的には ATP7B関連蛋白のCOMMD1の遺伝子のエクソン2領域の欠損)と考えられています。
慢性肝臓病には3つの進行ステージがあり、血液検査、X線検査、エコー(超音波診断装置)、病理組織検査などによって分類されます。
慢性肝臓病の初期では、目立った症状がほとんど現れません。
血液検査で肝機能検査ALT(GPT)、AST(GOT)などの上昇が大きく中期の段階で、ようやく症状が現れ始めます。
肝臓病の進行とともに目立つ症状
犬の慢性肝臓病が進行すると、以下のような症状が目立つようになります。
- 食欲不振、体重減少(痩身)
- よく眠る(嗜眠)
- 散歩量の低下(元気消失)
- 動かない時間が増える
- 急に老化した印象
- 毛並み、毛づやが悪くなる
- 下痢や嘔吐
- 多飲多尿
- 黄疸
- 腹水
- 出血が止まりにくい
- 肝性脳症
…など。
これらの症状は肝臓病がかなり進行するまで現れません。
気になる症状が現れたらすぐに動物病院で受診しましょう。
犬の肝臓病は早期発見と食事療法が重要
犬の慢性肝臓病は、初期では症状が現れません。
そのため、慢性肝臓病を早期発見して、食事療法を早期に開始することが重要です。
犬の慢性肝臓病は、犬の年齢が中高齢で発症率が増加する傾向にあります。
慢性肝臓病を早期発見するために、愛犬がシニア期(6〜7歳)を迎えたら定期的な検診をおすすめします。
犬の肝臓病に療法食をおすすめする理由

犬の肝臓病(肝炎)用の食事療法では、肝臓に負担となるタンパク質を調整しつつ必要な栄養素を満たすことができるため、愛犬の健康の維持や回復に役立つことが多いです。
また、そのような理由から、手作りのレシピでは最適な栄養素にコントロールすることが困難なことが多いです。
愛犬をいたわる最適な療法食を取り入れましょう。
犬の肝臓病の療法食について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
「犬の肝臓病は早期発見と食事療法が重要」でご説明したように、肝臓は「沈黙の臓器」といわれるようにダメージがあっても症状に現れずらい臓器です。
肝臓病が増悪化する前に、適切な治療と食事療法を始めることが、愛犬のQOLを高めることにつながります。
肝臓の療法食の他にも、心臓・膵臓・皮膚・消化器、尿路結石症や食物アレルギーのサポートなどさまざまな療法食があり、症状に合わせて栄養バランスの量が調整されています。
手作りの食事は良くない?
犬の肝臓病に最適な栄養バランスの食事を用意するには、専門的な栄養知識が求められます。
そのため、手作りで肝臓病用の食事を用意するのは極めて困難です。
手作りレシピでよく紹介される牛肉などの肉類などを「トッピング」で与える、「レバー」を肝臓用の食材として利用するなどがありますが、避けたい食材です。
高アンモニア血症の原因となるタンパク質の過剰摂取になる可能性があるばかりでなく、遺伝的に弱い子においては銅の過剰蓄積による肝炎を悪化させる可能性があるためです。
このように、銅を多く含む赤肉、レバー、さつまいも、納豆などは手作りレシピでよく使われる食材ですが、肝臓病の進行を早めるおそれがあります。
肝臓病の食事は栄養素を正確に計測・計算する必要があるため、手作りで用意するよりも、最適な栄養・カロリーを配合した療法食の活用をおすすめします。
肝臓病療法食の4つのポイント

- 獣医師の診断・指導にもとづいて与える
- 療法食への切り替えは時間をかける
- 適正量を守る
- 新鮮な水をいつでも飲めるようにする
1. 獣医師の診断・指導にもとづいて与える
療法食は獣医師の診断・指導に基づいた食事療法として与える必要があります。
飼い主の中には、肝臓病を発症する前や予防目的で子犬の頃から療法食を与えようとする方がいますが、健康な犬に療法食を与えると必要な栄養素を十分に摂取できず健康を損なうおそれがあります。
2. 療法食への切り替えは時間をかける
肝臓病療法食を与えはじめるときは、1か月程度の時間をかけてゆっくりと切り替えましょう。
療法食は通常のドッグフードと味が異なるため、フードを急に切り替えると愛犬が味の変化にとまどい、食欲不振になることがあります。
普段食べているドッグフードに療法食を徐々に混ぜ、少しずつ慣らしていくのがポイントです。
3. 適正量を守る
療法食は少量でも必要な栄養素を摂取できるよう配合されているので、一般的なドッグフードより給餌量が少なくなります。
療法食の袋などに記載されている食事量を守って与えるようにしましょう。
食事量・ドッグフードの切り替えのポイントは、こちらの記事も参考にしてみてください。
4. 新鮮な水をいつでも飲めるようにする
肝臓病のステージが進行すると、たくさんの水を飲みますが、同時に多尿となる場合が多く、その場合は体内の水分量を確保できず、脱水症状になる危険性があります。
そのため、いつでも新鮮な水を飲めるように飲水を頻繁に交換する、水が飲める場所を複数設置するなど、愛犬が水分をしっかり摂れる環境を用意しましょう。
肝臓病療法食を食べない時は?
愛犬が肝臓病の食事を食べないときは、以下のような工夫をしてみましょう。
- フードを温める
- フードに水分を加えて柔らかくする
- 食事を数回に分けてあげる
- フードにトッピングする
療法食は通常のドッグフードと味が異なり、食いつきが悪くなることがあります。
また、犬の慢性肝臓病はステージが進むと食欲低下などの症状が現れます。
そのため、肝臓病療法食を食べないときは、上記のような工夫で愛犬の食欲をそそるようにしてあげましょう。
詳しい方法は『肝臓病の犬が食事を食べないときの対処法』についての記事をご覧ください。
愛犬の肝臓に良い食材が配合された療法食を
犬の慢性肝臓病は、一度かかってしまうと肝臓の機能を元に戻すことはできません。
そのため、早期に食事療法を開始することが愛犬のQOLを高めます。
肝臓病の愛犬のために、最適な栄養を配合した療法食を取り入れましょう。