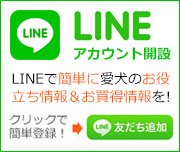犬の肝臓病の原因は?症状や治療法も解説
- 2022/10/31
- 肝臓の病気について
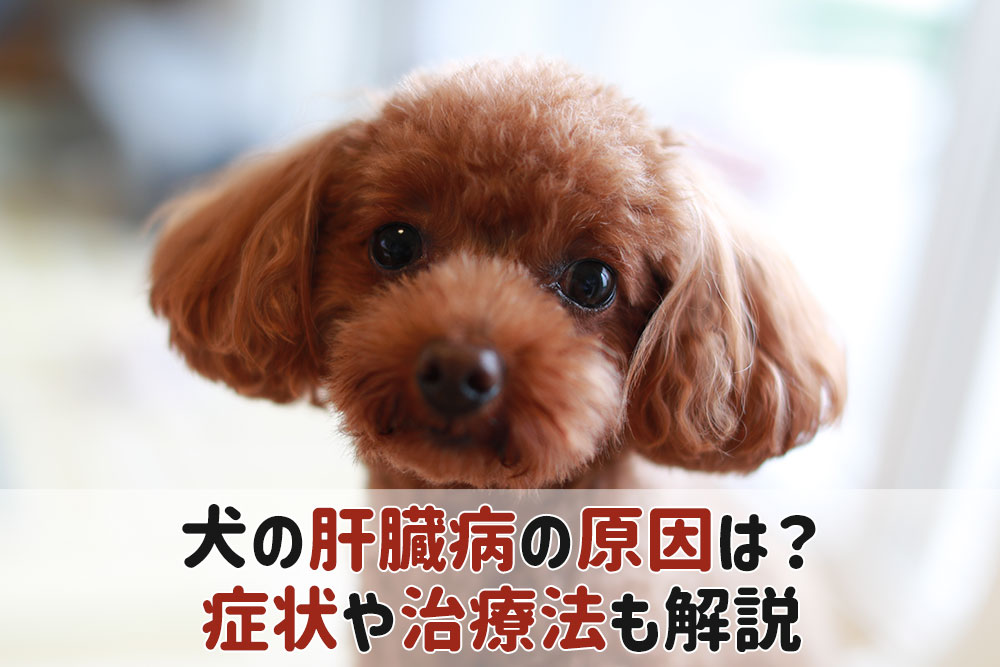
犬の肝臓病の原因は?症状や治療法も解説
犬の肝臓病(肝炎)の原因について、徹底解説します。
慢性肝臓病(肝炎)、急性肝臓病(肝炎)の原因と症状、治療法、食事療法のポイントについても詳しく紹介します。
目次
犬の肝臓病(肝炎)の原因は?ポイントまとめ
慢性肝臓病(肝炎)の原因は?
- 原因不明(特発性)の肝機能の低下
- 銅の蓄積が原因の肝機能の低下
- 感染による肝機能の低下
- 薬や化学物質による肝機能の低下
慢性肝臓病(肝炎)の症状は?
- 食欲不振、体重減少(痩身)
- よく眠る(嗜眠)
- 散歩量の低下(元気消失)
- 動かない時間が増える
- 急に老化した印象
- 毛並み、毛づやが悪くなる
- 下痢や嘔吐
- 多飲多尿
- 黄疸
- 腹水
- 出血が止まりにくい
- 肝性脳症
…など。
※初期、早期では無症状。
慢性肝臓病(肝炎)の治療法は?
- 肝臓病用の療法食で、悪化を防ぎ、回復を促す
- 肝臓への毒性が疑われる薬やサプリメント、食材などを中止する
- 早期に発見して治療することが重要
急性肝臓病(肝炎)の原因は?
- 肝毒性のある物の誤食、感染症、急性肝炎などによる急激な肝機能障害
- 感染、化学物質、薬品などによる中毒で起きる場合が多い
急性肝臓病(肝炎)の症状は?
- 急にぐったりする(元気消失)
- 嘔吐
- 食欲不振
- 多飲
- 発熱
- 脱水
- 黄疸
- 出血傾向(点状出血、吐血、メレナなど)
急性肝臓病(肝炎)の治療法は?
- できるだけ早く動物病院で受診しましょう
犬の肝臓病(肝炎)はどんな病気?
犬の肝臓病(肝炎)とは、肝臓が何らかのダメージを受けて機能が低下し、台車や解毒など、肝臓本来の働きができなくなる病気です。
犬の肝臓病(肝炎)には慢性肝臓病(肝炎)と急性肝臓病(肝炎)の2種類があり、原因や症状がそれぞれ違います。
- 慢性肝臓病(肝炎)…肝機能の低下が3ヶ月以上持続する病気
- 急性肝臓病(肝炎)…数時間〜数日の間に急激な肝機能の低下が起こる病気
| 慢性肝臓病(肝炎) | 急性腎障害 | |
|---|---|---|
| 状態 | 持続的な肝炎 | 数時間~数日間の急激な肝炎 |
| 原因 | 薬や毒物による肝機能低下、肝臓への銅の蓄積など | 農薬などの化学物質による肝毒性のあるものの誤食、感染症など |
| 腎機能の回復 | 見込める | 見込める ただし、重い急性肝炎の場合には危険 |
| 治療目標 | 肝機能の回復 | 肝機能の回復 |
犬の肝臓病(肝炎)の原因を詳しく解説

肝臓は、栄養素の分解、合成、貯蔵を行なったり、体の中の毒素を分解して無毒化したりといった、さまざまな重要なはたらきをする器官です。
肝臓病(肝炎)は、何らかの原因により、これらの働きが低下する病気です。
犬の慢性肝臓病(肝炎)の原因
犬の慢性肝臓病(肝炎)の原因は、主に原因がはっきり特定できない特発性にともなう肝炎です。
肝炎の原因として多い薬、サプリメント、食材などで疑わしいものを与えないようにします。
肝臓には動脈、静脈、門脈の3種類の血管があります。
門脈は、胃腸から吸収した栄養を消化管を通じて肝臓に送る働きをしています。
肝臓では流れてきた血液の老廃物や毒素を解毒します。
肝臓は有害なものを解毒し、胆汁を作り、腎臓からは尿として体に有害なものを排泄できるようにします。
肝臓はそれ以外にも、糖・蛋白質(タンパク質)・脂質・ホルモンの代謝、血液凝固(=出血を止める)因子の産生やビタミンの合成・貯蔵など、肝臓は非常に重要な役割を担っています。
犬の慢性肝臓病(肝炎)は、慢性的な肝細胞の死滅(壊死やアポトーシスなど)、炎症、再生と繊維化が特徴の病気で犬では一般的な疾患となります。
どの年齢でも発症しますが、特に中高年の犬は発症率が高くなる傾向があります。
比較的に雌で起きやすい傾向があり、慢性肝炎が起きやすい特定の犬種(ラブラドール・レトリバーなど)がいます。
また、感染症や癲癇(てんかん)、炎症などの病気の治療に使用する薬が、慢性肝臓病(肝炎)の原因になることもあります。
犬の急性肝臓病(肝炎)の原因
犬の急性肝臓病(肝炎)の主な原因には、感染症・化学物質・薬品などのよる中毒で起きることが多いです。
毒物摂取、感染症など
犬の急性肝臓病(肝炎)の主な原因のひとつに、肝臓に毒性のある物の誤食や、感染症(レプトスピラ症など)があります。
犬の急性肝臓病(肝炎)の原因となるのは、以下のようなものです。
<感染が原因>
- 犬アデノウイルス1
- レストスピラ
- 敗血症
<中毒物質や薬が原因>
- キシリトール(ガムなどに多く使用される甘味料で急性肝壊死を起こす)
- 農薬、殺鼠剤
- アセトアミノフェン(人の風邪薬や痛み止めで危険性が高い)
- ソテツの実(日本の暖かい地域で発生が多い)
- カビ毒(海外で汚染されたフードなどで発生)
- てんかん薬
- 抗菌剤
- 抗がん剤
…など。
肝細胞の傷害
犬の急性肝臓病(肝炎)は、中度レベル以上では、繰り返す嘔吐が見られます。さらに重度になると黄疸、血便、神経症状などの症状が起こることもあります。
多臓器不全となり、死に至る可能性もあります。
また、日本は高温多湿な気候の上、夏場のアスファルトが高温になるため、熱中症となり、それが引き金で急性肝臓病(肝炎)など多臓器の障害に発展し、命に関わる問題に発展することが多く見られます。
キシリトール
ありふれたガムが、急性肝臓病(肝炎)の原因になることがあります。
キシリトールを使用したガムは特に危険で、急性肝壊死を起こして亡くなることもあるため注意する必要があります。
人に役立つ食材や薬であっても、進化の系統の異なる犬では命の危険を生じさせることが多く発生します。
人の食材や薬、ハーブなどを与える事には注意が必要です。
犬の肝臓病(肝炎)の症状は?

犬の慢性肝臓病(肝炎)の症状
初期はほとんど症状がないため気が付かないことが多いです。
慢性肝臓病の発見は、ワクチン接種や定期検診などでみつかることが多いです。
慢性肝炎の症状は中レベル以上での悪化で見られることが多いです。
犬の慢性肝臓病(肝炎)の症状は、進行状況により変化していきます。
慢性肝臓病(肝炎)は、血液検査によるALT(GPT)、AST(GOT)、ALT、GGT(γ-GTP)などの数値を考慮して診断されます。
| 値 | 概要 |
|---|---|
| ALT(GPT) | ALTはアラニンアミノ基転移酵素の略称であり、以前はGPTと呼ばれていました。 ALTは、細胞が壊れた際に血液中に漏れ出る逸脱酵素です。 ALTはほとんど肝臓に存在する酵素なので、肝細胞障害検出の特異度が高い重要な血液検査項目です。 |
| AST(GOT) | ASTはアスパラギン酸アミノ基転移酵素の略称であり、以前はGOTと呼ばれていました。 ASTは、細胞が壊れた際に血液中に漏れ出る逸脱酵素です。 |
| ALP | ALPはアルカリフォスファターゼの略称で、誘導因子により産生される誘導酵素です。 ALPは、生体の細胞膜に広く分布していますが、特に肝臓や胆道系に多く含まれているので、肝胆道系疾患で上昇します。 |
犬の慢性肝臓病(肝炎)は、主に以下のような症状が見られます。
- 食欲不振、体重減少(痩身)
- よく眠る(嗜眠)
- 散歩量の低下(元気消失)
- 動かない時間が増える
- 急に老化した印象
- 毛並み、毛づやが悪くなる
- 下痢や嘔吐
- 多飲多尿
- 黄疸
- 腹水
- 出血が止まりにくい
- 肝性脳症
※初期、早期では無症状
犬の慢性肝臓病(肝炎)の初期・早期段階は、ほぼ無症状です。
中期では嘔吐、食欲不振など症状が現れ始めます。末期では激しい嘔吐、下痢、黄疸、元気消失などの症状が現れます。
急性肝臓病(肝炎)の症状は?
犬の急性肝臓病(肝炎)の症状は、発症から数時間〜数日で急激に現れます。
急性肝臓病(肝炎)の症状は、主に以下のようなものです。
- 急にぐったりする(元気消失)
- 嘔吐
- 食欲不振
- 多飲
- 発熱
- 脱水
- 黄疸
- 出血傾向(点状出血、吐血、メレナなど)
犬の急性肝臓病(肝炎)は、食欲が低下して食事を食べなくなる、嘔吐を繰り返すなど、多飲、発熱などの症状が見られます。
さらに、急性肝臓病(肝炎)が進行すると脱水、黄疸、出血傾向(点状出血、メレナなど)の症状が現れます。
犬の肝臓病(肝炎)の治療法は?

犬の慢性肝臓病(肝炎)の治療
犬の慢性肝臓病(肝炎)は、原因特定などが難しい場合が多いですが、適切な治療を受けた犬の健康は良好に維持されることが多いです、
そのため、原因や疑わしい要因を排除し、食事療法などで肝臓の回復を促し、健康を維持する治療法が用いられます。
慢性肝臓病での食事療法は、肝臓や脳神経系への負担の軽減のために、タンパク質を少なく調整したフードの使用が検討されることが多いです。
犬の慢性肝臓病(肝炎)の初期・早期の段階では、症状がほとんど現れません。
動物病院でのワクチン接種、定期健康診断などにより気づく場合が多いです。
とくに、犬の年齢が中高年になると慢性肝臓病(肝炎)の発症率が増加する傾向にあります。
この年齢の頃からは特に定期的に検査することが、病気の早期発見につながります。
定期検査のほかにも、気になる症状が現れたらすぐに獣医師の診察を受けるようにしましょう。
犬の急性肝臓病(肝炎)の治療
犬の急性肝臓病(肝炎)の治療には、動物病院での点滴や投薬が必要です。
急性肝臓病(肝炎)と思われる症状が見られたら、すぐに動物病院で診察してもらいましょう。
急性肝臓病(肝炎)は、治療が遅れると命に危険を及ぼします。
急性肝臓病(肝炎)が進行すると肝細胞壊死により、生命にかかわる大変に危険な状態となります。
そのため、動物病院で速やかに治療する必要があります。
犬の肝臓病(肝炎)に良い食べ物と食事療法のポイント
慢性肝臓病(肝炎)では肝臓病(肝炎)用の食事療法をとりいれ、肝臓への負担を抑えて病気の回復をサポートすることが重要です。
肝臓病(肝炎)用の食事療法では、肝臓に負担となるタンパク質を調整しつつ必要な栄養素を満たすことが必要で、そのような食事が役立つ場合が多くあります。
そのため、手作りのレシピでは最適な栄養素にコントロールすることが困難なことが多いです。
犬の慢性肝臓病(肝炎)の食事療法で重要なのは、主に以下のポイントです。
- タンパク質の制限
- 必須のビタミンなど微量栄養素の補給
- ミネラルの調整
- 効率的なエネルギー補給
食事療法で早めのケアを
<犬の慢性肝臓病(肝炎)を早期発見して食事療法を始めることが、愛犬の健康維持につながります。
慢性肝臓病(肝炎)に最適なタンパク質、リン・カルシウム・亜鉛などのミネラルバランス、エネルギーの効率的な補給などを計算・調整された、愛犬の肝臓の健康をサポートする療法食を取り入れてみましょう。